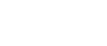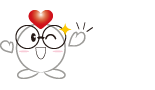弱視には、メガネなどで矯正しても視力が出ないことを意味する法律用語や一般用語としての「弱視」(社会的弱視)と、医学用語としての「弱視」(医学的弱視)とがあります。ここでは、後者について、快適視生活応援団に以前私が連載した「子供の視力と弱視について」の記載から抜粋して説明いたします。
■1.弱視とは
視力は、生まれてから外界からの視覚入力(視性刺激)を経験しながら、発達するものです。生後すぐの赤ちゃんでも、眼球や脳への経路はほぼ完成していますので、視覚反応はあります。しかし、見えるということは、目に入った情報が脳に届いて、見えたものの形、色といった属性がわかり、見えたものが母親の顔か、食べ物か、静物かといった意味がわかってきて、初めて視力を得たとなるわけですから、外界からの視覚体験が重要なわけです。こうして、3歳ぐらいまでに視力は急速に発達し、5歳頃には視力検査をするとほとんどの子どもが1.0以上の視力を得ます。
ところが、眼球や脳に何ら器質的問題がないのに、何らかの理由でこの視力の発達がうまくいかなかったり、遅れたりした場合を医学的に「弱視」として扱うのです。

■2.弱視の種類と対策
弱視の種類は、より治りにくいものから順に列挙しますと、視性刺激遮断弱視、斜視弱視、不同視弱視、屈折性弱視の順で、このような4種類に分類します。
(1)視性刺激遮断弱視
このちょっとむずかしげな名前の弱視は、その視性刺激が何らかの原因で遮断されることで生ずる弱視です。 特に問題なのは、片目に眼帯をしたり、目や目のまわりの病気やけがのために片目が閉じている状態が生じて、視性刺激が片眼だけに入力されるような事態です。 この場合、視性刺激が入らない方の目に弱視が発生します。両眼同様に刺激が入りにくい場合に比べ、片眼だけに刺激が入りにくい場合のほうが、圧倒的に弱視になる可能性が高いのです。
このため、生後から3~4歳くらいまでは、眼科医は不必要に眼帯を使いません。それは片眼の視性刺激を人為的に遮断することになるからです。この時期では、1日眼帯するだけでも、弱視が発生する可能性があると考えられます。
(2)斜視弱視
人間はだてに両眼があるのではなく、両眼でものを見て初めて距離感や立体感を得ることができます。これを両眼視機能といい、人間のような高等動物にしか発達していない機能です。
斜視とは、視線がまっすぐでない状態ですが、学問的には両眼視機能が十分に発達していない状態と定義されています。つまり、斜視があると優位眼(利き目) ばかりで見るようになり、非優位には視性刺激が入りにくくなり、弱視になるのです。斜視の治療は、その種類、状態によっていろいろで、適切な時期に手術をする必要があるものもあります。一般眼科では扱わないこともあるので、斜視が疑われたら、小児眼科や神経眼科のある施設を受診して、方針を決めることが必要です。
(3)不同視弱視
例えば、右目は正視(近視、遠視、乱視がない状態)で、左眼は強い遠視だったとします。このような左右眼の屈折に著しく差がある状態を、不同視とよびます。この例の場合、遠方も近方もピントがあわせやすい正視眼で見ることになります。 そうすると、強い遠視の左眼は、あまり使いません。つまり、視性刺激の入力が 乏しくなるため、視力の育ちが悪くなるのです。これが、不同視弱視です。これも早めに見つけて、適正な眼鏡などをかけさせる必要があります。
(4)屈折性弱視
強い遠視、近視や乱視があるのに、子供のときに必要なメガネをかけず、明瞭な像が脳に届かなかったために視力の発達に支障を生じたための視を、屈折性弱視といい、通常両眼とも視力が十分出にくい状態です。9~10歳くらいまでは、子供の脳は柔軟性があり、まだ発達する潜在力がありますから、それまでに正しい矯正レンズをかけることにより、少々遅ればせながら、視機能の発達を促せる可能性があります。屈折性弱視は、弱視のうちでも、最も治りやすいものですが、適正な眼鏡をかけさせる時期が遅れると、うまく治らないこともあります。
よく、子どもにメガネをかけさせるのは可哀想だという親の話を聞きますが、明瞭な像が脳に届かなければ、視力の発達だけでなく、脳機能の発達にも影響しかねません。医師に相談の上、適切な対処を行うことが大切です。

執筆:医療法人社団 済安堂 井上眼科病院院長 若倉雅登